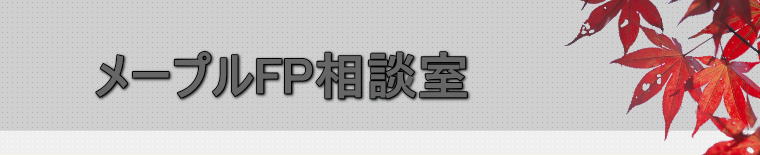|
|
 |
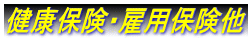
日本の社会保険制度には、疾病に対応する健康保険、失業に対応する雇用保険、労働災害に対応する労災保険、介護に対応する介護保険と言ったものがあります。基本は強制加入の保険で、事故が起こった時に現金ないしは現物給付により生活を保障する相互扶助の制度です。
大切なことは、原則自己申告により保険の補償を受けることが出来るので、各保険の内容をよく理解しておくことが大変重要です。
健康保険
これは皆さんに一番馴染みのあるもので、病気やけがをした時の療養の給付が受けられるものです。健保の一部負担金は義務教育就学前は2割、一般は3割、70〜74歳は2割となっており、75歳以上は『後期高齢者医療制度』へ移行し、1割負担となります。
健康保険には、大きく分けて国民健康保険、協会健康保険、組合健康保険の3種類があります。一般に給与所得者が加入する協会健保、組合健保では傷病手当金や出産手当金が支給されます。
傷病手当金は意外と見落とされがちですが、鬱などの長期疾病に罹り、退職した場合でも勤務中に加入していた健保に所定の書類を提出すれば、最大で1年半の間、傷病手当金が支給されます。
また、長期療養、入院などによって、1ヵ月の自己負担額が高額になる場合には、高額療養費制度があり、1ヶ月の自己負担限度額が決まっています。この高額療養費制度も組合健保の場合には組合によって付加給付と言って限度額を独自に低く設定している場合もあります。
雇用保険
雇用主と労働者が保険料を負担して、失業した場合に基本手当を受け取れる制度として知られていますが、それ以外にも就業促進手当や高齢者の急激な給与減に対応する高年齢雇用継続基本給付金などもあります。また育児休業、介護休業期間の無給に対応する給付金や、厚労省が指定する教育訓練を受講した場合にも給付金がこの雇用保険から支給されます。
労災保険
雇用主が全額保険料を支払い、業務災害、通勤災害での療養は一部負担なく10割給付となり、休業補償給付もあります。
介護保険
若い方には馴染みがないかもしれませんが、40歳から健康保険と合わせて保険料の支払いが始まり、64歳までは第2号被保険者ということで、加齢に起因する疾病での介護状態でしか給付は受けられません。65歳からは一般的には年金から保険料が天引きされ、介護状態によって介護給付、予防給付が受けられます。
急速な高齢化の影響で、従来自己負担額が一律1割であったものが、2015年8月から一定以上所得のある方は2割負担になります。
以上のように、我が国には色々な公的保険制度がありますので、もし何かあったら、公的保険制度でどの程度カバーされるかをネット等で調べられることをお勧めします。
医療保険等に加入する時も社会保険でどこまでカバーされるか理解できれば、むやみに補償額を広げ、多額な保険料を払わなくても済むかも知れません。

 |
|
|